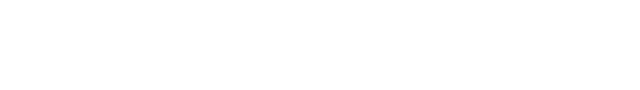慢性疲労症候群
慢性疲労症候群とは
病気や寝不足、過労などの明らかな原因はないが、生活に支障が出るほどの疲労が6か月以上続く疾患
疾患自体の原因はまだ不明ですが、脳や体のなんらかの異常が原因といわれています
症状
6か月以上にわたり症状がある
微熱
のどの痛み
頸部などリンパ節の腫れ
筋肉痛や筋力低下
倦怠感
頭痛
関節痛
精神症状:集中力低下、うつ症状など
不眠
など
検査
原因が不明のため、確定診断となる検査はありません
それ以外の疾患を否定していく必要があります
貧血やカリウム、カルシウムなどの電解質異常、甲状腺機能低下症、
悪性腫瘍、自己免疫疾患など
診断
厚生省の診断基準が用いられることが多いです
・次の大基準2項目に加えて、小基準の「症状基準8項目」以上か、
「症状基準6項目+身体基準2項目」以上を満たすと「慢性疲労症候群」と診断されます
・大基準2項目に該当するが、小基準で診断基準を満たさない場合は、「慢性疲労症候群うたがい」となります
A.大クライテリア(大基準)
1.生活が著しく損なわれるような強い疲労を主症状とし、
少なくとも6ヶ月以上の期間持続ないし再発を繰り返す(50%以上の期間認められること)
2.病歴、身体所見.検査所見で
悪性腫瘍、自己免疫疾患、急性・慢性細菌感染症、HIV感染症、
慢性炎症性疾患、神経筋疾患、内分泌疾患、呼吸器疾患、
循環器疾患、消化器疾患などを除外する
B.小クライテリア(小基準)
ア)症状クライテリア(症状基準)
(以下の症状が6カ月以上にわたり持続または繰り返し生ずること)
1. 微熱(腋窩温37.2~38.3℃)ないし悪寒
2. 咽頭痛
3. 頚部あるいは腋窩リンパ節の腫張
4. 原因不明の筋力低下
5. 筋肉痛ないし不快感
6. 軽い労作後に24時間以上続く全身倦怠感
7. 頭痛
8. 腫脹や発赤を伴わない移動性関節痛
9. 精神神経症状(いずれか1つ以上)
羞明、一過性暗点、物忘れ、易刺激性、錯乱、思考力低下、集中力低下、抑うつ
10. 睡眠障害(過眠、不眠)
11. 発症時、主たる症状が数時間から数日の間に発現
イ)身体所見クライテリア(身体所見基準)(2回以上、医師が確認)
1. 微熱、2. 非浸出性咽頭炎、3. リンパ節の腫大(頚部、腋窩リンパ節)
疲労度を客観的に表すためPS(performance status)が用いられます
慢性疲労症候群では、PS3以上となります
PS(performance status)による疲労・倦怠の程度
(旧厚生省 慢性疲労症候群診断基準(試案)より抜粋)3)
0: 倦怠感がなく平常の生活ができ、制限を受けることなく行動できる
1: 通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 倦怠感を感ずるときがしばしばある
2: 通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 全身倦怠の為、しばしば休息が必要である
3: 全身倦怠の為、月に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である
4: 全身倦怠の為、週に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である
5: 通常の社会生活や労働は困難である。軽作業は可能であるが、 週のうち数日は自宅にて休息が必要である
6: 調子のよい日は軽作業は可能であるが、 週のうち50%以上は自宅にて休息している
7: 身の回りのことはでき、介助も不要ではあるが、 通常の社会生活や軽作業は不可能である
8: 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、 日中の50%以上は就床している
9: 身の回りのことはできず、常に介助がいり、 終日就床を必要としている
治療
原因不明のため対症療法となります
1.ビタミンB群の投与
(当院ではアリナミンやメコバラミンの処方、ネオラミン投与など)
2.漢方薬(補中益気湯や人参養栄湯、加味帰脾湯など)
3.生活習慣・運動習慣の見直し
当院では
内科疾患を鑑別して
原因が明らかとなれば、その対応をします(ビタミン補充など)
原因が分からない場合、
精神疾患の鑑別のため精神科や心療内科の受診を勧める、
漢方薬の内服を開始する、
などを検討します